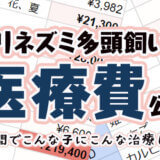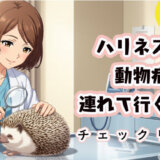痛い、辛い、調子悪い……。人間なら言葉で伝えられる不調も、ハリネズミは飼い主にはっきりと教えてくれません。だから飼い主が毎日、彼らのわずかな変化を感じ取ってあげる必要があります。ここでは、注意すべきハリネズミの不調のサインや、動物病院での診察に向けた準備についてまとめてみました。
目次
【症状別】こんな変化には注意

まずは、ハリネズミに見られる変化と、そこから疑われる病気の例を、ハリんちの飼育経験と見聞きした情報の範囲内でまとめました。
ごはんの食べ方が変(クチャクチャ、遅い、片側で噛む)
ごはんの食べ方に違和感があれば、歯肉炎の兆候かもしれません。ハリネズミには歯のトラブルが多いようで、体感では2歳を超えたあたりから増える印象です。
歯肉炎の歯はむず痒かったり痛んだりするので、ハリちゃんたちもその歯を使いたがりません。だから頭を傾けて食べ物を片側に寄せて噛んだり、ごはんを食べきるのに時間がかかるなどの変化が見られるようになります。
歯肉炎でぐらついた歯は、獣医さんの判断で抜歯することがあります。抜歯によって痛みの原因を取り除き、食事しやすくなるようにするのです。
歯ぎしりをしている
これも歯肉炎が疑われます。歯がむず痒くてこすっているのかもしれません。
寝ているときなどに鳴き声のような音がする
ハリちゃんと一緒に暮らしていて、“寝言”みたいに鳴いたのを聞いた経験はありませんか? いびきなのか寝言なのか不明ですが、どんな子もたまに言いますよね。
問題は「頻繁に」鳴く場合ですが、ハリんちでは姫ちゃんが毎回のように寝ながら謎の鳴き声を出していたものの、それが原因で何か病気が見つかったわけではありませんでした。個体差で気道が狭い子だったのかもしれません。
ごはんを残す

単なる偏食、歯肉炎、ストレス、消化器疾患などいろいろです。ハリんちでは、他に目立った症状がなければ様子見をする可能性が高いのですが、様子見をして良いか安易に判断することなく、慎重に検討します。
カキカキが長い
コミカルな見た目で癒やされるカキカキの仕草も、1日に何度も、10秒とか長い時間続くようなら怪しいです。ダニかもしれません。実はハリんちでも、5歳の子(咲ちゃん)がある日ダニにやられていました。室内飼育で毎日の掃除で清潔にしていたのに、どこからかダニが進入して咲ちゃんに寄生したのですね。長いカキカキと緑色便という2つの症状が出たので受診したところ、ダニ陽性。緑色便はダニによるストレスから来るものだろうということで、月1回の駆除薬(レボリューション)投与を4ヶ月続けて治しました。緑色便は最初のレボリューション投与後すぐに収まりました。
フケや抜け針が多い
ダニ感染または真菌(白癬菌)感染症、あるいはその両方が併発している場合の症状です。どちらも人間も感染対象(人獣共通感染症)なので、注意が必要です。ただ、室内が乾燥してフケが多くなったり、生え替わり時期で抜け針が増えたりと、その原因がダニでも真菌でもない場合もあって、飼い主が目視で判断するのには限界があります。
うんちがゆるい

緑色便ではないけれどもうんちが日常的にゆるい場合、まずは消化器のトラブルが疑われますが、軽度~重度まで幅があります。軽度でも慢性的な場合、診察後に腸内環境改善のサプリを処方されたりして、長く付き合う疾患となります。
緑色便をした
緑色便を出す原因はいろいろあります。ストレスか肝臓・胆嚢(胆汁)疾患が主なものですが、前者は軽度、後者は重度なので判断が難しいです。小さい子をお迎えしてすぐにストレスで出す緑色便と、肝臓機能の低下で肝硬変を発症して出す緑色便は、同じ緑色便でも大きく違います。後者の場合は全身が黄緑色がかって見える「黄疸」が出る場合もあったりします。食欲は前者でも後者でも落ちることがあるのでややこしいです。
ちなみに人間の黄疸は肌が黄色っぽくなりますが、ハリネズミの黄疸は緑寄りの黄緑色になります。ハリんちではいちごちゃんに肝臓由来の黄疸が出ました。
おしっこに血が混じっている
2歳を過ぎたメスのハリネズミのケージを掃除するときに、おしっこをしたところに薄いピンク色が混じっていたら、まず子宮疾患(良性・悪性の両方で、子宮筋腫、子宮内膜過形成、重度で子宮蓄膿症など)を疑うのが定石のようです。ハリんちでは子宮疾患で子宮卵巣摘出手術をした子が4名いて、割合(手術した子÷ハリんちの全女子)は1/3を少し下回る程度。「多い」と言えるでしょう。
この血尿、初めて遭遇すると飼い主的に慌ててしまうと思います。ですが本人は(血尿が出始めた初期は)特に痛みもなく、食欲も変わりないはずです。落ち着いて受診して検査と前準備を済ませ、摘出手術をしてもらいましょう。ハリんちでもみんな手術後ケロッとして普段通りの生活に戻りました。
ちなみに、おしっこに血が混じる原因のひとつには膀胱炎などの泌尿器疾患もありますが、ハリネズミではそれほど多くないようです。
体の一部にしこりがある
抱っこしてお腹を触ったときにコリコリとした感触がある場合、腫瘍の可能性があるので、早めの受診をお勧めします。ただ、これが思ったより気付きにくいです。体の外にこぶが出ていればまだしも、柔らかいモフ毛と皮下脂肪の下のコリコリは、だいぶ神経を集中させて触らないとわからないかもしれません。
ハリんちでは、毎日抱っこしていたララちゃんの皮下にできたコリコリ(扁平上皮癌)になかなか気付けず、その難しさを体感しました。
くしゃみをしている
風邪を引いてしまったかもしれません。ハリネズミは鼻腔の構造上、蓄膿症(副鼻腔炎)が慢性化しやすいようで、早めに治療して治さないと、長く付き合う病気になってしまう可能性があります。
ハリんちでは、すき間風対策が不十分で数名が同時に風邪を引いてしまい、投薬でもなかなか改善できず慢性化した子たち(咲ちゃん、ちくわくん)がいます。症状は突然くしゃみをするだけと軽いものですが、別の病気にかかった時に弱い呼吸器に影響が出るのは必然なので、現在は特に寝床づくりに注意を払っています。
鼻水が出ている
これもくしゃみと同様、呼吸器疾患の症状です。咲ちゃんが毎年冬場は鼻づまりを起こし、1週間に1回ぐらいのペースで青っぱなを出しています。慢性化してだいぶ経ってからもレントゲンで改めて診てもらいましたが、鼻腔の奥に蓄膿があり、先生からも「食欲など影響が出なければ付き合う方向で」と指導を受けています。
なんとなく全身の色がおかしい
緑色便のところでも書きましたが、“なんとなく”全身の色がおかしいなと思った子がいました(いちごちゃんです)。別の子と並べてよくよく観察してみたところ、緑色がかっていることがわかって、「ああ、これは黄疸かも」と。受診して検査したら、肝臓が悪くなっていることがわかりました。
「色」を見れば良いのですぐに気付きそうなものですが、他の子と見比べないと確信が持てなかったので、わかりにくい変化かなと思います。
ちなみに、黄疸は溶血や肝臓・胆道の障害などが原因で起こる、放っておくのはマズい症状です。
吐いた
何かを食べて吐いた、ぐらいであれば様子見で大丈夫だと思いますが、何日も吐くようなら深刻な疾患の可能性があります。しんくんは嘔吐が数日続いて受診したところ、肝硬変が見つかりました。
吐く現場を目撃できれば良いのですが、夜吐いたものを朝、飼い主が吐瀉物だと気付くには少しコツがいると思います。白い泡が付いていたり、黄色みがかった液体だったり、うんちやおしっことは微妙にちがうので、気をつけないと見逃してしまうでしょう。
歩き方が変
突然片方の後ろ脚がストンと抜けるようにコケたり、ズルッと横滑りしたり、プルプルと揺れたりしているような動きが何日か続くようであれば、WHS(Wobbly Hedgehog Syndrome、ハリネズミふらつき症候群)の疑いが出てきます。
WHSは生前の確定診断はできないと言われていて、受診後は投薬をしつつその子の状態に合わせて付き合い、生活環境を工夫するというターミナルケアが中心になると思います。
そうではなく、片脚を上げながら歩く場合は捻挫や骨折の可能性があります。この場合も早めに受診した方が良いでしょう。ハリんちではいちごちゃんがテーブルから落ちて捻挫した経験はあります。痛み止めの飲み薬だけで数日で良くなりました。骨折は経験なくわかりません。
体重が急に減った・増えた
体重の急な増減は、何でもない場合から重篤な場合まで幅のある変化のひとつです。なぜ体重が変化したのかを考えて、原因を探っていくと良いと思います。ごはんの給餌量・消費量はいつも通りなのに「増えた」場合、運動時間が減ったことが原因かもしれません。ではなぜ運動時間が減ったのか。爪が伸びていて走りづらい? 歩くとどこかが痛むから? といったように、なぜ?を深掘りしてみると良いと思います。
逆に、ごはんの給餌量・消費量はいつも通りなのに「減った」場合、成長期であればごはんの量が足りていないと考えられ、高齢であれば甲状腺機能亢進症の疑いも出てきます。天と地ほどの差がありますよね。
ごはんを残して体重が「減った」場合、消化器疾患、糖尿病、腎臓病など重篤な病気のサインとなりますが、気まぐれな偏食でごはんを残して減ったのかもしれません。
このように、体重増減だけでは判断が難しいので、ハリんちでは他に変化がないかを探り、それらの情報を総合して通院すべきか否かを判断しています。
何をあげても全く食べない
あれもダメ、これもダメ。偏食かなと思ってフードを変えたり、補助食品をあげてみたりしても、ほぼ何も食べない。あるいは、ミルワームだけは食べる、果物だけは食べる。これはもはや偏食ではなく、何か食べられない理由があると考えましょう。早めに受診することをお勧めします。
診断には幅があると思います。歯肉炎で歯が痛むので食べられない、風邪を引いて体調が悪く食べたくない、胃腸や肝臓の疾患で食欲が出ないなど……。
ハリんちでは、ララちゃんが1ヶ月半ぐらいかけて少しずつ食べなくなり、最初は偏食かなとフードを変えていたら食べるものが出てきていたものの、少しずつ残すようになって、何も食べなくなりました。受診して調べてもらったところ、右下腹部の皮下に扁平上皮癌ができており、しかも下顎リンパ節と鼠径リンパ節にすでに転移していました。執筆現在もステロイドを服用しつつ、ターミナルケアを行っているところです。
足の指の股が裂けて出血
特に1歳未満など若い子でありがちなのが、夜中にホイールを爆走した翌朝、ホイールからケージの床、ペットシーツなどに血の跡が散らばっているという事件です。ハリんちでも何名も経験しましたが、血はすぐ止まりますし、そのうち出血しなくなるので、念のため足湯で清潔にしてあげるだけで、様子見で良いかと思います。
触らせてくれない子はどうやってチェックする?
ハリネズミにはビビりな子が多いので、飼い主といえど触らせてくれない子もいると思います。そういう子のチェックで重宝するのは、100円ショップでも手に入る「虫かご」など。透明なケースに入ってもらうことで、上から下からよく観察できるようになります。とはいえ、ハリんちとしては、日頃から触られ慣れてもらうことも大事だなと考えています。病院に行けば、知らない場所で知らない人(獣医さん)に触られるわけで、それは大きなストレスです。そのストレスを少しでも減らすためにも、普段から飼い主の手からおやつをあげるなど、手が触れることがプラスになると考えてもらえるようにするのがお勧めです。
また、知らない場所への耐性を養う意味で、ご自宅でもケージの外に囲いをつくってあげたりして、探検してもらうことも効果的だと思います。
病気関連の記事
ハリんちで経験したハリネズミの病気についての記事です。併せて参考になれば幸いです。
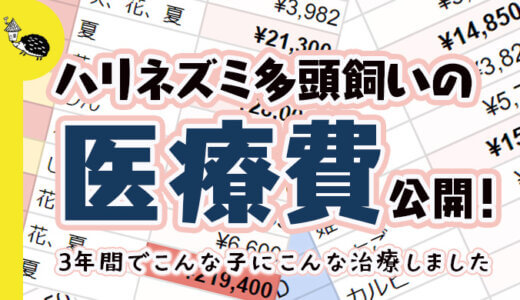 ハリネズミ多頭飼いの医療費公開! 3年間でこんな子にこんな治療しました
ハリネズミ多頭飼いの医療費公開! 3年間でこんな子にこんな治療しました  病気になったハリネズミのお世話のコツ&病気の予防
病気になったハリネズミのお世話のコツ&病気の予防  運動不足のいちごちゃんが捻挫を期に運動するようになった話
運動不足のいちごちゃんが捻挫を期に運動するようになった話  炎症性腸疾患?原因不明の体調不良で逝去したさくらちゃん
炎症性腸疾患?原因不明の体調不良で逝去したさくらちゃん  姫ちゃん2歳8カ月の子宮卵巣摘出手術
姫ちゃん2歳8カ月の子宮卵巣摘出手術  小さく産まれた子の先天性心臓疾患
小さく産まれた子の先天性心臓疾患  おちんちんが腫れた元気くん、動物病院へ
おちんちんが腫れた元気くん、動物病院へ  朝起きるとふらついてる…大吉くん通院記
朝起きるとふらついてる…大吉くん通院記  コロちゃんの難産:3日間に渡った出産、死産、母体の危険
コロちゃんの難産:3日間に渡った出産、死産、母体の危険  蕾ちゃんの闘病記:良性腫瘍の切除~腎臓病由来の重度の貧血、突然のお別れ
蕾ちゃんの闘病記:良性腫瘍の切除~腎臓病由来の重度の貧血、突然のお別れ  健太郎くん闘病記:後ろ脚麻痺・最期の六日間
健太郎くん闘病記:後ろ脚麻痺・最期の六日間  ハリネズミの皮膚トラブル:夏場の肌の乾燥
ハリネズミの皮膚トラブル:夏場の肌の乾燥  ハリネズミ蕾ちゃんの皮膚トラブル!かゆくて傷に | 子育て&成長日記32
ハリネズミ蕾ちゃんの皮膚トラブル!かゆくて傷に | 子育て&成長日記32  健太郎くんの軟便―ハリネズミの子育て&成長日記28(シーズン2)
健太郎くんの軟便―ハリネズミの子育て&成長日記28(シーズン2)  三太郎の“消えたシッポ”-ハリネズミの子育て&成長日記19(シーズン1.5)-
三太郎の“消えたシッポ”-ハリネズミの子育て&成長日記19(シーズン1.5)- 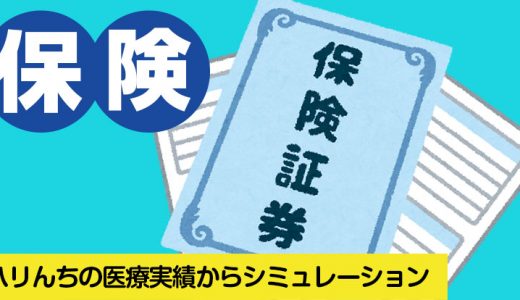 ハリネズミの病気と「保険」|2社の保険商品に入っていたらどうなった?
ハリネズミの病気と「保険」|2社の保険商品に入っていたらどうなった?  ハリネズミの「病気」と保険|ハリんちの通院実績と内容ご紹介
ハリネズミの「病気」と保険|ハリんちの通院実績と内容ご紹介  ハリネズミを診てくれる動物病院リスト:大阪市近郊編
ハリネズミを診てくれる動物病院リスト:大阪市近郊編 Amazonのアソシエイトとして、ハリんちは適格販売により収入を得ています。